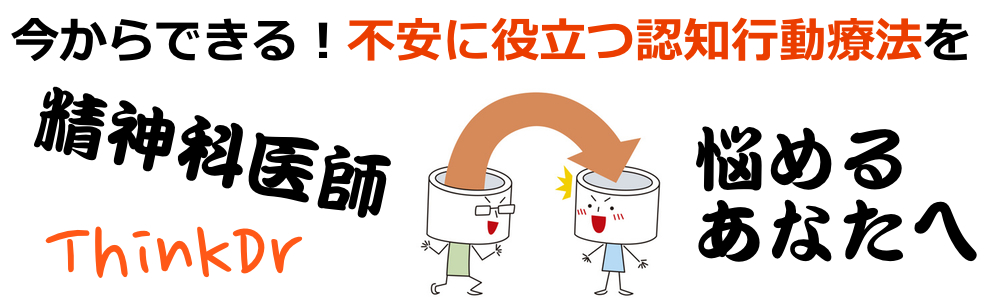言語が脳を支配する。旧日本軍の失敗。
日本では言葉は言霊といわれ不思議な力を持つとされてきました。
今回は言語が脳を支配してしまうということです。

By: Pier Fumagalli
言語が脳を支配するやり方
言霊では言葉を口に出すと実現すると言われています。
しかし、口に出さないで脳で考えている方が言葉の支配力は高まります。
太平洋戦争での日本軍
太平洋戦争で日本軍は言霊の力を恐れていたと言われます。
「負ける。」という言葉を使うと本当に負けるから負けるとは言えなかったのです。
負けるという言葉を使わなければ負けたときの作戦は立てられません。
負け始めた時に有効な作戦を立てられなかった原因の一つとされます。
負けるという言葉を使わなかったのに
日本軍は負けてしまいました。
言霊の力とは幻想だったのでしょうか。
それは違います。
「負ける。」と言えない状況の中で
日本軍の指揮官の脳の中では
「負ける。」という言葉がどんどん増殖していきます。
現在の脳科学では言葉は口に出すときではなく
思考の中で大きな力を発揮すると言われます。
言葉が脳で働く流れ
「負ける。」という言葉を口に出せない状況は
実は脳の中で「負ける。」という言葉が広がるのに好都合です。
例えば
「ピンクの象だけは思い浮かべないでください。」
そう言われて、ピンクの象を一生懸命押さえようとすると
ピンクの象が頭から離れません。
このように言葉は否定しようと思えば思うほど
その言葉の影響が強まるという特徴を持ちます。
言語の支配から脱するためには
言語は否定されることで脳を支配していくことを説明しました。
この支配から抜け出すためにはどうすれば良いのでしょうか。
否定的な言語は押さえようとせずそのままおいておく
言葉は押さえると増えます。
そのため、否定せずにそのままにする方が効果的です。
試験の結果が不安であれば
大丈夫と言い聞かせるのでも、解決策をあれこれと悩むのでもなく
あ、自分は明日の試験結果が気になっているんだ、と気づくことです。
人間の脳は問題解決の為に発達してきました。
一つの問題の解決方法をあれこれ考える時に特化しています。
しかし、試験結果のようにもう何も変わらないときでも
同じ働きをしてしまうから問題です。
何を考えても明日の試験の結果の不安は消えません。
不安が消えないと脳はまだ問題は解決していないと判断して
さらに一生懸命不安に対応していくこととなります。
別の言葉を入れる
そのままにしておいてもそのうち不安は増大していきます。
押さえようとするとさらに大きくなります。
次に必要なことは他の言葉を入れることです。
例えば旅行の計画を立てるなどはいかがでしょうか。
なんだ、気をそらせば良いのか。そんなことで不安が消えるならそうしてるよ。
そう考える方が多いかもしれません。
その通りです。不安は消えません。
むしろ、不安を無くすために気をそらすのであれば
不安を考えないようにしていることと同じで
余計に不安は高まっていきます。
気をそらすためではなく、
その時に不安が無かったらしているだろうことを不安があっても考えていって
不安に気づいてもそのままにしておくことが必要です。
言語が脳を支配する仕組みと、その支配からの抜け出し方でした。